
はるか昔ヨーロッパの地で安全に飲める水の確保が難しかった時代、ワインは水よりも安全性の高い飲み物として位置付けられ、人々の生活に無くてはならない存在でした。
そうしてワインはヨーロッパの食文化に深く関わり、その土地それぞれの風土や人々の嗜好性を反映しながら発展し、ついには「マリアージュ」の概念を生み出すまでに至りました。
マリアージュ
「マリアージュ」これは簡単に言うと相性のことです。それぞれが引き立てあったり、補いあったりすることでそれぞれの旨みや個性がさらに発揮されるような組み合わせが理想とされます。
肉料理には赤いワイン、魚料理には白ワイン

マリアージュと言われて最初に頭に浮かぶフレーズは「肉料理には赤いワイン、魚料理には白ワイン」ではないでしょうか。これは主な料理に着目して分かりやすく二分化して説明した言葉なので、本来はもう少し詳しい説明が必要です。
ワインの味わいは色に関わらず、スタイルや産地など様々な要素によって変化しますし、料理も素材の旬や調理法、ソースや薬味の合わせ方によって変化しますので、全体の料理の構成を考えたうえでワインを組み合わせなければなりません。
その時や場所に合った組み合わせを
いつ、どこで、誰と、どんな目的で飲むのか。家で普段楽しむなら家庭料理に合うワイン、各地方の特産品を使った伝統料理にはその土地のワイン、ホテルやレストランで提供されるような手の込んだ料理には複雑で厚みのある味わいのワインを。
ワインの産地や生産者、熟成年数などを考えて料理を合わせ、質と量と金額についても配慮しつつそれぞれのシーンに合わせてワインと料理の格に差が出ないように心がけます。

濃度を合わせる
料理とワインを合わせる時、それぞれの味わいの濃度を合わせてみましょう。
牛肉や豚肉は赤身の肉で濃い食材、鶏肉のような白身の肉は軽い食材として考えます。調理法においても、火を通した料理や食材に厚みのあるものは、食感が出て旨みを感じやすくなるので重口のワインを合わせた方がよいでしょう。
同じ鶏肉を使った料理でも、調理法や合わせるソースによって選ぶワインは変わってきます。
例)
・牛や羊肉の料理 → 重口の赤
・生ハム、スモークサーモン → 軽口のロゼ
・鶏のレモン塩焼き → 軽口の白
・鶏のクリーム煮込み → 重口の白
・鶏の赤ワイン煮込み → 中程度の赤
風味を合わせる
ワインを飲む時にグラスを回して香りを嗅ぐ光景をよく目にします。それは、香りがワインの味わいのなかの一つの要素として重要な役割を果たしているからです。
そのため、ワインと料理のマリアージュを考える際は、風味を合わせるということも重要です。スパイシーな料理にはスパイシーなワイン、ハーブを使った料理にはハーブの香りのワイン、スイーツにはデザートワインといった具合です。
例)
・スパイシーな四川料理 → スパイシーなニュアンスの赤(シラーなど)
・かぼすを搾った白身のお刺身 → 柑橘の風味を持つ白(ソーヴィニヨンブランなど)
地域を合わせる「日本ワインと和食」
国内で製造された日本ワインは、繊細な和食と良く合うと考えられます。日本固有品種の白ブドウ(甲州)を使用したワインには柚子やカボスの風味があり和食にマッチします。また黒ブドウ(マスカットべーリーA)は和食に欠かせない醤油との相性が良く魚料理にも合います。
例:赤ワイン)
・お醤油で食べるキノコおろし → 軽口の赤(マスカットベーリーA)
・たれで食べる焼き鳥 → 中間的な味わいの赤(ブラッククイーン)
・豚の角煮 → やや重口で優しい味わいの赤(メルロー)
・馬刺しのカルパッチョ黒こしょう風味 → 重口の赤(シラー)
例:白ワイン)
・柚子やカボスを搾る天ぷら → 辛口の白(甲州)
・青しそドレッシングのサラダ → 辛口の白(ソーヴィニヨンブラン)
・サワラの西京焼き → ほのかな甘みの白(リースリング)

反対方向のもので合わせる
あんこに少しの塩を足す、スイカに塩をかけて食べる。塩の引き締め効果でさらに甘みが引き立つという関係です。反対方向のものを合わせることで、それぞれにない要素を補いあいます。代表的なマリアージュとしてはブルーチーズと貴腐ワインが上げられます。
反対方向のもので合わせる組み合わせは上級者向けの組み合わせでその実例は限られたものになります。例えば「スイーツ」×「辛口ワイン」という組み合わせはワインの酸味が必要以上に際立ってしまうことが多く、難易度が高いものだと言えるでしょう。
ここで、ボルドーの有名シャトーのマダムが提案した驚きのマリアージュをご紹介致します。
それは、「ワサビ豆」×「貴腐ワイン」と「干し梅」×「貴腐ワイン」です。
ぴりりとした舌を刺すワサビの辛みとふくよかなワインの甘さがお互いを引き立て合い、半生の干し梅は酸味が柑橘系の香りと似ているのでそれぞれの余韻が気持ちよく残ります。これもまた方向の全く違うもの同士を組み合わせた一例です。
赤ワインと料理の合わせ方例
・(フルボディ)香りが力強く濃厚なワイン → 脂っぽい料理
・(ミディアムボディ)コクと酸味のバランスのよいワイン → 濃い味付けの魚介類、軽口の肉料理
・(ライトボディ)軽いフレッシュなタイプ → 脂ののった魚料理、軽口の肉料理
白ワインと料理の合わせ方例
・樽熟成でコクのある辛口 → 軽口の肉料理でソースは濃厚に、エビやカニなど甲殻類
・酸味の穏やかな辛口 → 白身魚のお刺身
・酸味の効いたフレッシュな辛口 → 野菜やキノコ類、鶏のささみ
・酸味も味わいも柔らかな中辛口 → おでんなど出汁のきいた和食
・フルーティな甘口 → 前菜やデザート
ロゼと料理の合わせ方例
ロゼワインは白ワインと赤ワインの中間的な存在なので、生ハムやサーモンに代表されるようなマリアージュだけでなく様々な料理とも相性が良いワインです。
・すっきりとした辛口 → 野菜の煮込み、辛みの効いた料理
・フルーティな甘口 → 前菜やデザート
スパークリングと料理の合わせ方

料理との相性でどんなワインを選べば良いか迷ったらスパークリングワインがオススメ。
なかでもシャンパーニュ製法で作られたワインは瓶内二次発酵という製法により繊細で複雑な風味を特徴とし、どんな料理とも合わせやすい万能選手だと言えるでしょう。
まとめ
ワインと料理のマリアージュは元来ヨーロッパの食文化です。ですので、日本人である私達には馴染みのない部分もあります。
しかし、日本ワインと和食という組み合わせならどうでしょう? かつてヨーロッパで発展してきたように、日本の固有品種である甲州やマスカットベーリーAやブラッククイーンは日本の風土に育まれた日本ワインとして、和食とともに日本ならではのマリアージュが構築され、発展していくものと考えます。
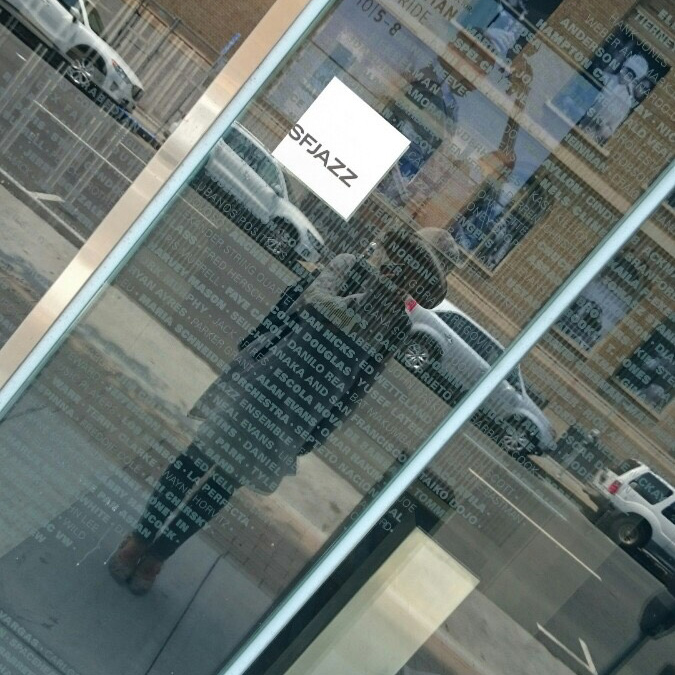
長野県出身 40代女性 10数年の修行を経て小さなBARの経営者になる。独立後さらにお酒の道を極めるべくワインソムリエ資格(日本ソムリエ協会(JSA))とチーズプロフェッショナル資格取得(NPO法人チーズプロフェッショナル協会)。お酒の声の代弁者として日々研鑽中。


